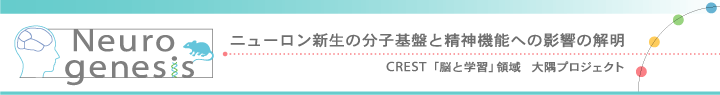 |
|||||||||||||
|

前号から引き続き伊佐氏との対談をお届けします。 大隅 脊髄損傷の研究を始められて、研究の出口を意識されるようになりましたか。 伊佐 これから、リハビリにつながる話はいろいろと出てくるのではないかと思います。すぐに、応用までいかなくても、臨床の現場で聞く話が、どういう脳の働きのためにおこっているのか、仕組みを説明できるようになると思います。たとえば、リハビリ中の患者さんで、昨日はやる気があって随分上手になったけれども、今日は機嫌が悪くてやる気がないから、上手にできないということを、理学療法士から聞きます。これは、脳の中の意欲にかかわる神経回路と、運動を制御する神経回路につながりがあることを示しているのかもしれない。 大隅 それは、アスリートのトレーニングでも同じでしょうね。 伊佐 そうです。意欲を引き出す工夫が、治療に使えないかと考えますよね。こういう話を一般の人にすると、どうしたら意欲を高められますかと必ず聞かれます。ぼくは、それがわかったら自分でやりますと言っています。(笑) 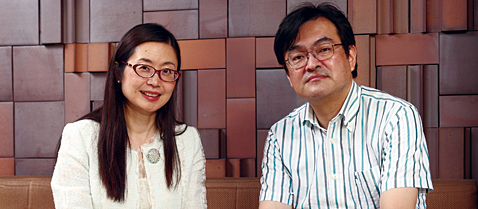 大隅 学生さんに利用するとか。(笑)ところで、最近非常に着目されているブレインマシンインターフェース(BMI)について、先生も研究をなさるのですね。 伊佐 是非ともやりたいと思っています。BMIは、今後、システム神経科学が発展していく中で、避けて通れない道だと思います。一つには、役に立つ研究ができるという意味があります。脳の信号を読み取ることは、外界に対する働きかけが非常に限られている状態の患者さんにとって福音になる可能性があります。 大隅 ただ、機械が自分を動かすといったことに対する抵抗感のある方はいらっしゃいますね。 伊佐 脳に対する介入は、気持ちが悪いという見方は強くあると思います。コーヒーを飲んで、カフェインをとり、気分を整えることだって、ある意味では脳への介入なのですが、より直接的なかたちを取ると抵抗感が出てくる。一方、パーキンソン病の治療で、脳の深部に電極をうめこむ深部脳刺激(DBS)という治療は、安全性も向上し、かなり社会に受け入れられてきています。
伊佐 ええ。倫理観については、常にボーダーラインがあると思います。しかし、このようなボーダーラインは、その時々の知識や、リスク・ベネフィットのバランスによってかなり変わるものだと思うんです。たとえば、60〜70年代に、精神科の病棟で電気ショックが、治療目的だけではなくて、懲罰的な意味で使われていた。現在では、電気ショックは、ちゃんとコントロールをかけて行うと、うつ病に対して効果的な治療だと言われています。どこにボーダーラインを引くかはあらかじめ決まっているのではなくて、その時々の科学技術の到達点がどのあたりにあるのかによって変わる。神経科学と社会との接点で起こりうる問題について考える「脳神経倫理」が今後、重要になってくると思います。 大隅 「脳神経倫理」についてはどのようにお考えですか? 伊佐 研究者は、何か夢があるから研究をしているので、できそうなこととか、これからできるかもしれないことについて、楽天的に語ってしまう傾向があります。ただ、それが一般社会に伝わったときに、どう受け取られるのかは、別の次元の問題です。例えば、クローン技術などについては大隅先生はどのようにお考えですか? 大隅 断片的な技術はすべてクリアしているので、それを全部やってしまうと、クローン人間はまったく不可能ではない。私たち研究者は、やってはいけないことだろうと線を引いていますが、どこかの大金持ちがまったくプライベートの研究所で科学者を雇えばできる。 伊佐 いまのクローンの技術は、本当に完全なクローン人間が作れるような状況ではないかもしれないけれど、ある一定の確率でできてしまう可能性はある、ということですね。今、科学者である自分が話していることはいまの科学で本当にできてしまうことなのか、それとも単にできたらいいなと思っていることなのか、混同せずに科学の現状を正確に伝えるサイエンスコミュニケーションは重要だと思います。 大隅 正しく伝えるには、具体的に個別に、例えばこういう事例がもしあったとしたらどう考えるか。そういうふうに考えていかないとだめですね。 伊佐 ええ。これは、ここまでできるけれども、どういう場合なら応用していいというように、具体的な議論をしないと、倫理の問題というのは先へ進まない感じがします。 大隅 たとえばBMIでは、どこまで行けそうですか。
大隅 意図を読み取る方法は。 伊佐 米国では、脳に剣山のような電極を刺して、神経細胞の活動を読み取る研究がされていますが、電極の耐久性の問題など、クリアしなくていけない課題がまだまだ残されています。10年、20年使えないといけないのですが、現状はそうなってはいません。そこで目指すべきもう一つの方向として、針を刺すのではなくて、脳波、特に大脳皮質の表面から記録する皮質脳波(ECoG)を使う方法が注目されています。ハンディキャップが少ない人に関しては、より非侵襲的な方法で、近赤外線や脳波を使う。より重度の障害で、切実度が高い人の一部は、より侵襲的な方法も採りえるのだろうと思います。 大隅 近赤外線より脳波ですか。 伊佐 勿論侵襲度に違いがあるので適用の範囲が異なりますが。取り出せる情報に関しては、特に皮質脳波が有利だろうと思います。いずれにせよ、サルをモデルとして皮質脳波がどのような情報を持っているかを明らかにするといった基礎的な研究がもっと必要です。 大隅 脳から読み取るところの研究をちゃんと進めないと、それを応用するというところに行かないですよね。  伊佐 はい。もう一つの問題は、フィードバックです。たとえば腕を伸ばしてコップをつかむという命令を脳が出して、腕を伸ばすとします。最初に腕を伸ばした方向だとコップからちょっとずれていたという情報が脳に戻り、今度は、ほんの少し右にずらすとか、微調整しながら、腕の動きを制御しています。BMIでも、フィードバックをちゃんと戻して、はじめて正確さが実現されるはずです。こうして、BMIの方法や考え方を使うことで、逆に、フィードバックを使って脳が何をやっているのかという問題が解けるきっかけになるかもしれないと考えています。 大隅 応用に近い研究をすることが、原理原則というか、真理の探求とか、そういった方向に役に立つかもしれない。双方向性ですね。 伊佐 ええ、双方向性は必ずあると思います。また、ひょっとしたら、脳の報酬系の中枢を刺激することによって、ある種のリハビリを促進するとか、そういったこともできるのではないかという期待もあります。もちろん。どこまで許されるかという問題はありますが、そういうことを追求することで、逆に報酬系と学習の問題が明確になってくるかもしれない。BMIのアウトプットはもちろん大事なのですが、その過程で神経科学として非常に重要な問題もいくつか存在している。それが、今後の研究に期待しているところでもあります。
|
||||||||||||
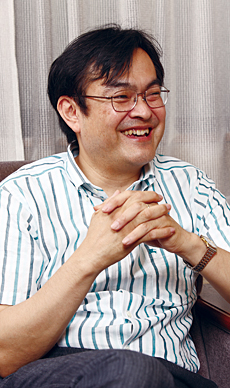 大隅 何をどこまで認めてもいいかということは、集団の価値観によりますね。
大隅 何をどこまで認めてもいいかということは、集団の価値観によりますね。 伊佐 手足を動かすことができない患者さんの意図を読み取って、パソコンのカーソルを動かすとか、手紙が書ける段階にすでになっています。ただし、それは、患者さんがたくさん訓練をして初めてできるようなことなのです。最終的には、脳の働きをよる深く理解することで訓練なしで誰でもできるレベルにする必要があります。その点は5年か10年でかなり進むのではないかと思います。
伊佐 手足を動かすことができない患者さんの意図を読み取って、パソコンのカーソルを動かすとか、手紙が書ける段階にすでになっています。ただし、それは、患者さんがたくさん訓練をして初めてできるようなことなのです。最終的には、脳の働きをよる深く理解することで訓練なしで誰でもできるレベルにする必要があります。その点は5年か10年でかなり進むのではないかと思います。